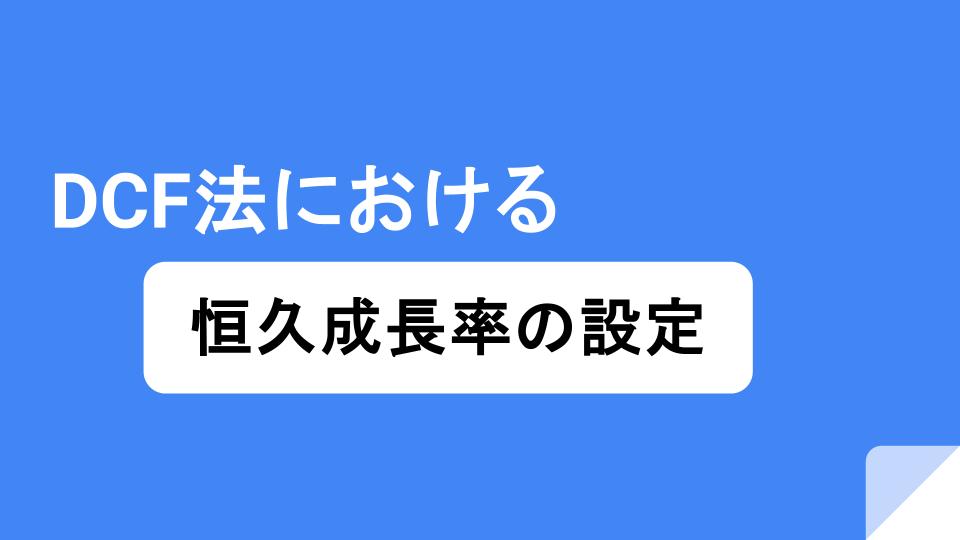DCF法による企業価値算定は、一定期間の詳細な事業計画を前提とする「予測期間」と、その後の事業継続を評価する「継続価値(ターミナルバリュー)」に分けて構成されるのが一般的です。
この継続価値の代表的な算出方法として、マーケットアプローチ的なマルチプル法と、インカムアプローチ的な恒久成長率法およびバリュードライバー式による算出方法が挙げられます。
本記事では、これらの算定方法のうち、実務で一般的に用いられている恒久成長率法に絞って、恒久成長率をどのように考えるべきかを整理します。
恒久成長率法による継続価値算定の基本構造
将来のキャッシュ・フローを永久に予測することは現実的ではありません。恒久成長率法では、予測期間最終年度の翌期以降、フリー・キャッシュ・フローが恒久的に一定の成長率で成長していくと仮定し、その現在価値を算定します。以下の算式が一般的に用いられます。
継続価値 = 予測最終年度翌期のFCF ÷(WACC − 恒久成長率)
一方で、恒久成長率法は、成長率の設定次第で継続価値が大きく変動するという特徴を持っています。特に、WACCとの差が小さい場合、わずか値の違いが評価額に大きな影響を与えるため、恒久成長率はDCFにおける最も重要なインプットの一つです。
恒久成長率をどう考えるか ― インフレ率と実務感覚
恒久成長率を検討する際には、まず割引率であるWACCの性質を理解しておく必要があります。一般に、WACCは名目ベースで算定されており、その中には期待インフレ率が織り込まれていると解釈されます。将来キャッシュ・フローも名目ベースで予測している以上、恒久成長率についても名目の成長率として考えるのが自然です。
この前提に立つと、恒久成長率の下限はインフレ率程度と考えることが妥当だと筆者は考えています。加えて、長期的な経済成長率(GDP成長率や業界成長率)をどの程度見込むのかという観点も検討する必要があります。筆者としては、恒久成長率は「インフレ率+予測経済成長率(実質)」を基本的な考え方として設定すべきだと考えています。
もっとも、日本の評価実務においては、将来の不確実性や説明可能性を重視し、恒久成長率を0%程度に抑えて設定するケースも少なくありません。
一方で、恒久成長率をインフレ率以下に設定するということは、その企業が名目ベースでは横ばいであっても、実質ベースでは縮小していく前提を置いていることを意味します。この点は慣行として自動的に採用されるべきものではなく、評価者が意識的に選択すべき重要な前提だと考えています。
感応度分析によるリスクの可視化
恒久成長率は将来にわたる仮定である以上、単一の数値に過度に依存することは適切ではありません。実務では、恒久成長率とWACCを変数とした感応度分析を行い、前提の変化が企業価値に与える影響を把握することが一般的です。
特に、割引率が低く、恒久成長率が高い領域では、両者の差がわずかに変化するだけで評価額が大きく変動します。感応度分析を通じて、評価モデルがどの前提に対して影響を受けやすいのかを把握することは、評価結果を解釈するうえで欠かせません。
実務上は、中心シナリオの評価額だけでなく、前提が一定程度変動した場合のレンジを把握し、その中でどの水準を意思決定に用いるのかを検討する姿勢が求められます。
事例:清水建設による日本道路のTOBにおける恒久成長率の扱い
恒久成長率が実務でどのように設定されているかを示す事例として、2025年に公表された清水建設による日本道路のTOBを見てみます。
本件では、第三者算定機関による株式価値算定においてDCF法が採用されており、継続価値の算定方法として恒久成長率法とEXITマルチプル法の双方が用いられています。公開買付届出書によれば、恒久成長率法における恒久成長率は、▲0.5%から+0.5%という、ゼロ%近傍のレンジで設定されています。
また、割引率(WACC)についても単一の数値ではなく、6%台から7%台のレンジで前提が置かれており、恒久成長率とあわせて感応度を持たせた評価が行われています。特定の一点を固定するのではなく、前提の幅を示したうえで株式価値レンジを提示するという点は、実務的なDCF評価の特徴といえます。
この事例から分かるのは、恒久成長率はゼロ%前後の水準が用いられていること、そして恒久成長率やWACCはレンジで設定され、その感応度を含めて評価されていることです。
マルチプル法とのクロスチェック
恒久成長率法は理論的一貫性の高い手法である一方、前提に対する感度が高いという特性を持っています。そのため、実務ではマルチプル法によるクロスチェックを併用することが一般的です。
マルチプル法では、予測最終年度のEBITDAなどの財務指標に、類似企業のデータから導かれる倍率を乗じて継続価値を算定します。この方法は、市場参加者の評価水準を直感的に反映できる点が特徴です。
さらに、マルチプル法によって算定された継続価値から逆算し、「その評価が意味する恒久成長率はどの程度か」を確認することで、恒久成長率法の前提が過度に楽観的、あるいは保守的になっていないかを検証することができます。結果が大きく乖離している場合には、恒久成長率や割引率、あるいはマルチプルの前提に再検討の余地があると考えるべきでしょう。
まとめ
恒久成長率法における恒久成長率は、DCF評価の中でも特に影響度の高い前提です。恒久成長率をどの水準に置くかは、単なる数値選択ではなく、対象企業を長期的にどのような姿として捉えるのかという評価者の判断そのものを反映します。
インフレ環境や長期的な経済成長を踏まえつつ、感応度分析やマルチプル法によるクロスチェックを通じて前提の妥当性を検証することが、実務における恒久成長率設定の基本姿勢といえます。
参考文献
1:清水建設株式会社「公開買付届出書」
【免責事項(ディスクレーマー)】
本記事の内容は、コーポレートファイナンスの理論および一般的な財務モデリング実務に基づく解説を目的としたものであり、特定の案件に対する法務、税務、または会計上の助言を構成するものではありません。
税制(繰越期間、損金算入制限率など)は、対象企業の規模や管轄、税制改正等により大きく異なります。実際のM&A実務やバリュエーションにおいては、必ず公認会計士、税理士、弁護士等の専門家に最新の法令及び適用可能性を確認した上で、自己の責任において判断を行ってください。本記事の内容に基づき生じたいかなる損害についても、筆者および当サイトは一切の責任を負いません。